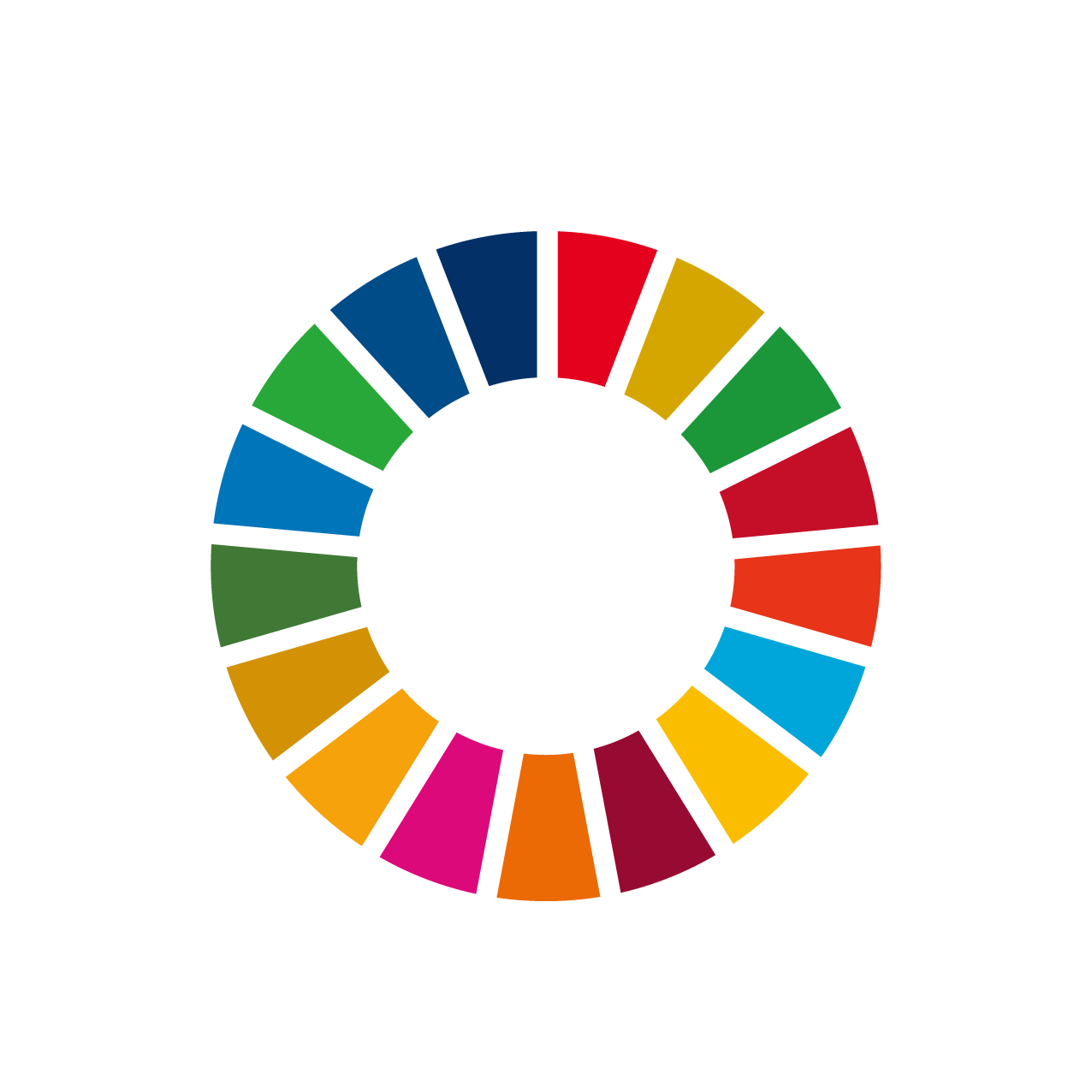診療科からのお知らせ
部門概要
医師が患者さんの病気を診断したり、治療計画を立てたりする上で種々の臨床検査データは欠くことのできないものとなっています。患者さんには採血を受けていただくことも多いかと思いますが、これらの検査を専門的に行う部署が検査部です。ここでは採血した血液ばかりではなく、便や尿、細胞や組織、患者さんご自身も検査対象となります。検査部は、扱う検体の種類や検査の方法、目的などにより検体検査、細菌検査、生理機能検査、病理検査、の4部門より構成されており、それぞれ専門の臨床検査技師により24時間体制で検査を実施し、患者さんのために精度の高い検査結果を提供しています。
検査内容
血液検査
血液に含まれる赤血球、白血球、血小板、血色素量等を測定することで、貧血や血液の病気がわかります。
血液凝固検査では出血傾向や血液凝固能の異常に関して調べます。
一般検査
尿検査では尿中の蛋白・糖・ウロビリノーゲン等の有無を検査し、必要に応じて蛋白・尿糖の定量検査を行います。また、尿に含まれる上皮細胞、赤血球、白血球、細菌等を顕微鏡を使って調べ、癌細胞が発見されることもあります。
便潜血検査は消化管出血の有無を検査します。インフルエンザウイルス抗原の検査なども行います。
生化学検査
体の状態を知る上で必要不可欠の検査です。肝機能検査・腎機能検査・脂質検査・電解質検査等、項目は多数あり、大型の自動分析装置で測定しています。迅速かつ正確性を要求されます。糖尿病の検査は血糖・HbA1cの検査を行います。
免疫検査
感染症・腫瘍マーカー・甲状腺ホルモン・婦人科ホルモン・血中薬物濃度検査等を行います。
輸血検査
手術・出血・重度貧血等で輸血が必要になった時に患者さんの血液型、不規則性抗体の有無、および血液製剤と適合するか否かの交差適合試験を行います。
細菌検査
提出された検体(喀痰・尿・膿・血液・髄液・体腔液など)を培養して、病原菌の有無を調べ、その菌に対する感受性検査(各種抗生剤の効き具合)を調べます。また、ここ数年は、新型コロナウイルスのPCR検査にも対応しています。
生理機能検査
生理機能検査は生体から生ずる微弱な活動電位や生体現象を電子機器を用いて測定する検査で、心電図・肺機能・脳波・筋電図・神経伝導検査・血圧脈波検査、聴力検査等があります。画像診断検査では、心臓の超音波検査を検査部で担当しています。
病理検査
手術、試験切除、内視鏡下生検で採取された組織の標本作製を行い、病理医による病理診断が行われています。また、手術時病変の広がりが肉眼では判断できない場合などに術中迅速診断が必要になりますが、病理医が常勤対応しています。 婦人科材料・尿・喀痰・体腔液・穿刺物(乳腺、甲状腺、リンパ節等)検体から癌細胞の有無なども検査しています。
採血業務・他
毎日、中央処置室で外来患者さんの採血・採尿受付けおよび採血業務を行っています。患者さんの血液や尿などは、検査部で血液検査、生化学検査、一般検査等を行います。 発熱外来では、新型コロナウイルスの遺伝子検査、インフルエンザ抗原検査を実施しています。